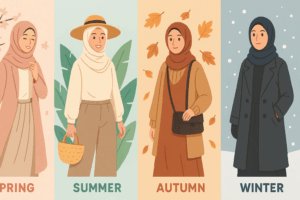近年、日本の大学では「ハラールフード」を提供する学生食堂が増えています。ハラールフードとは、イスラム教の教えに沿って許可されている食材や料理のこと。ムスリム(イスラム教徒)の人々は、豚肉やアルコールなど、戒律で禁じられた食材を避ける必要があるため、食事環境は非常に重要です。
世界各国からの留学生が増える中、多様性に対応する大学の取り組みが注目されています。
上智大学の本格対応
東京都にある上智大学では、2016年にハラール専門の学食「東京ハラルデリ&カフェ」を四谷キャンパス内にオープン。宗教法人日本イスラーム文化センターの認証を取得し、食材・調味料だけでなく、厨房や調理器具もすべてハラール基準に準拠しています。
同大学では2015年からハラール弁当の販売も行っており、多い日には150食が完売するほどの人気。そのニーズに応えるかたちで専門食堂が誕生しました。
APUは開学当初から
大分県の立命館アジア太平洋大学(APU)は、約半数が国際学生という国際色豊かなキャンパス。なかでもインドネシア出身のムスリム学生が約400人在籍しており、国際学生の中では最大のグループを形成しています。
APUでは2000年の開学当初から、学生食堂でハラールフードの提供を開始。2015年にはNPO法人日本アジアハラール協会(NAHA)の「ムスリムフレンドリー認証」も取得しました。現在では、ベジタリアンメニューも取り入れた多文化共生型の食堂として進化を続けています。
日本の大学食堂にも、国際社会の風が吹き込んでいます。留学生が安心して学べる環境は、食からも広がっているのです。